
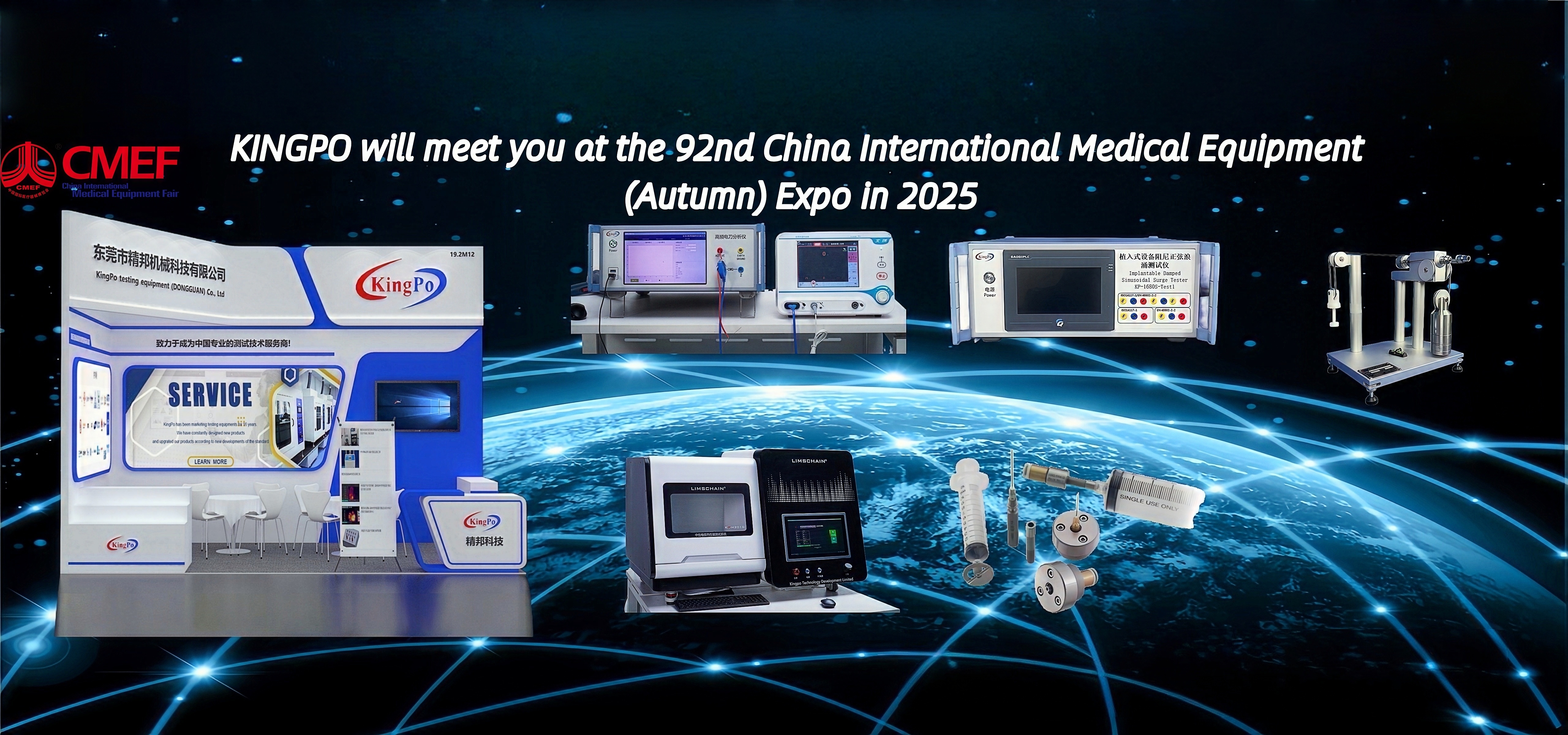
IEC 62368-1 オーディオアンプを搭載した機器の試験要件
ITU-R 468-4(サウンド放送におけるオーディオノイズレベルの測定)の仕様によると、1000Hzの周波数応答は0dB(以下の図を参照)であり、基準レベル信号として適しており、周波数の評価に便利です。![]()
オーディオアンプの応答性能。ピーク応答周波数信号。 メーカーがオーディオアンプが1000Hz条件下で動作しないことを宣言する場合、オーディオ信号源周波数はピーク応答周波数に置き換える必要があります。ピーク応答周波数は、オーディオアンプの意図された動作範囲内で、定格負荷インピーダンス(以下、スピーカーと呼ぶ)で最大出力電力を測定したときの信号源周波数です。実際の操作では、検査官は信号源振幅を固定し、周波数をスイープして、スピーカーに現れる最大実効値電圧に対応する信号源周波数がピーク応答周波数であることを確認できます。
最大出力電力は、スピーカーが取得できる最大電力であり、対応する電圧は最大実効値電圧です。一般的なオーディオアンプは、クラスABアンプの動作原理に基づいてOTLまたはOCL回路をよく使用します。1000Hzの正弦波オーディオ信号がオーディオアンプに入力され、増幅領域から飽和領域に入ると、信号振幅は増加を続けることができず、ピーク電圧点が制限され、フラットトップ歪みがピークに現れます。
オシロスコープを使用してスピーカーの出力波形をテストすると、信号が実効値まで増幅され、それ以上増加できなくなると、ピーク歪みが発生することがわかります(図2を参照)。このとき、最大出力電力状態に達したと見なされます。ピーク歪みが発生すると、出力波形のクレストファクターは、1.414の正弦波クレストファクターよりも低くなります(図2に示すように、クレストファクター=ピーク電圧/実効値電圧= 8.00 / 5.82≈1.375<1.414)![]()
図2:1000Hz正弦波信号入力条件、最大出力電力時のスピーカー出力波形
出力電力タイプと調整 - クリッピングのない出力電力クリッピングのない出力電力とは、スピーカーが最大出力電力で動作し、ピーク歪みがない場合の、飽和ゾーンと増幅ゾーンの接点での出力電力を指します(動作点は増幅ゾーンに偏っています)。オーディオ出力波形は、ピーク歪みやクリッピングのない完全な1000Hz正弦波を示し、そのRMS電圧も最大出力電力でのRMS電圧よりも低くなります(図3を参照)。
![]()
図3は、増幅率を下げた後の、クリッピングのない出力電力状態に入るスピーカーの出力波形を示しています(図2と3は同じオーディオアンプネットワークを示しています)
オーディオアンプは増幅領域と飽和領域のインターフェースで動作し、不安定であるため、信号振幅のジッター(上部と下部のピークが等しくない可能性がある)が発生する可能性があります。クレストファクターは、50%ピークツーピーク電圧をピーク電圧として使用して計算できます。図3では、ピーク電圧は0.5 × 13.10V = 6.550V、RMS電圧は4.632Vです。クレストファクター= ピーク電圧/ RMS電圧= 6.550 / 4.632≈ 1.414.出力電力タイプと調整 - 電力調整方法。オーディオアンプは、小さな信号入力を受け取り、それを増幅してスピーカーに出力します。ゲイン比は通常、詳細な音量スケールを使用して調整されます(たとえば、テレビの音量調整は30から100ステップの範囲です)。ただし、信号源振幅を調整してゲイン比を調整することは、はるかに効果がありません。信号源振幅を下げると、アンプのゲインが高くても、スピーカーの出力電力は大幅に低下します(図4を参照)。![]()
図4:信号源振幅を下げた後、スピーカーがクリッピングのない出力電力状態に入るときの出力波形。
(図2と4は同じオーディオアンプネットワークを示しています)
図3では、音量を調整すると、スピーカーは最大出力電力からクリッピングのない状態に戻り、RMS電圧は4.632Vです。図4では、信号源振幅を調整することにより、スピーカーは最大出力電力状態からクリッピングのない出力電力状態に調整され、実効値電圧は4.066Vです。電力計算式によると
出力電力=電圧RMSの2乗/スピーカーインピーダンス
図3のクリッピングのない出力電力は、図4のクリッピングのない出力電力を約30%上回っているため、図4は真のクリッピングのない出力電力状態ではありません。
最大出力電力状態からクリッピングのない出力電力状態に呼び戻す正しい方法は、信号源振幅を固定し、オーディオアンプの増幅率を調整すること、つまり、信号源振幅を変更せずにオーディオアンプの音量を調整することです。
オーディオアンプの通常の動作条件は、現実世界のスピーカーの最適な動作条件をシミュレートするように設計されています。現実世界の音響特性は大きく異なりますが、ほとんどの音のクレストファクターは4以内です(図5を参照)。![]()
図5:クレストファクターが4の現実世界の音波形
図5の音波形を例にとると、クレストファクター=ピーク電圧/ RMS電圧= 3.490 / 0.8718 = 4。歪みのないターゲットサウンドを実現するには、オーディオアンプは最大ピークがクリッピングしないことを確認する必要があります。1000Hzの正弦波信号源を基準として使用する場合、波形が歪みのないままで、3.490Vのピーク電圧が電流制限されないようにするには、RMS信号電圧は3.490V / 1.414 = 2.468Vである必要があります。ただし、ターゲットサウンドのRMS電圧はわずか0.8718Vです。したがって、ターゲットサウンドの1000Hz正弦波信号源のRMS電圧に対する低減率は0.8718 / 2.468 = 0.3532です。電力計算式によると、電圧RMS低減率は0.3532であり、これは出力電力低減率が0.3532の2乗であり、約0.125 = 1/8であることを意味します。
したがって、スピーカーの出力電力を1000Hz正弦波信号源に対応するクリッピングのない出力電力の1/8に調整することにより、歪みのないクレストファクターが4のターゲットサウンドを出力できます。言い換えれば、1000Hz正弦波信号源に対応するクリッピングのない出力電力の1/8は、クレストファクターが4のターゲットサウンドを損失なしに出力するためのオーディオアンプの最適な動作状態です。
オーディオアンプの動作状態は、スピーカーが1/8クリッピングのない出力電力を提供することに基づいています。クリッピングのない出力電力状態では、音量を調整して、実効値電圧が約35.32%、つまり1/8クリッピングのない出力電力に低下するようにします。ピンクノイズは実際の音に近いため、1000Hz正弦波信号を使用してクリッピングのない出力電力を取得した後、ピンクノイズを信号源として使用できます。ピンクノイズを信号源として使用する場合は、以下の図に示すように、ノイズ帯域幅を制限するために帯域通過フィルターを取り付ける必要があります。![]()
通常および異常な動作条件 - 通常の動作条件
さまざまなタイプのオーディオアンプ機器は、通常の動作条件を設定する際に、以下のすべての条件を考慮する必要があります。
- オーディオアンプの出力は、最も不利な定格負荷インピーダンス、または実際のスピーカー(提供されている場合)に接続されています。
——すべてのオーディオアンプチャンネルが同時に動作します。
- トーンジェネレーターユニットを備えたオルガンまたは同様の楽器の場合、1000 Hzの正弦波信号を使用する代わりに、2つのベースペダルキー(ある場合)と10個のマニュアルキーを任意の組み合わせで押します。すべてのストップと出力電力を増加させるボタンを有効にし、楽器を最大出力電力の1/8に調整します。
- オーディオアンプの意図された機能が2つのチャンネル間の位相差によって決定される場合、2つのチャンネルに適用される信号間の位相差は90°です。
マルチチャンネルオーディオアンプの場合、一部のチャンネルが独立して動作できない場合は、定格負荷インピーダンスを接続し、出力電力をアンプの設計されたクリッピングのない出力電力の1/8に調整します。
連続動作が不可能な場合、オーディオアンプは連続動作を可能にする最大出力電力レベルで動作します。
通常および異常な動作条件 - 異常な動作条件
オーディオアンプの異常な動作条件は、通常の動作条件に基づいて発生する可能性のある最も不利な状況をシミュレートすることです。スピーカーは、音量を調整したり、スピーカーを短絡させたりするなどして、ゼロと最大出力電力の間の最も不利な点で動作させることができます。
通常および異常な動作条件 - 温度上昇試験配置
オーディオアンプの温度上昇試験を実施する場合は、メーカーが指定した位置に配置してください。特別な記載がない場合は、前面が開いた木製の試験箱に、箱の前面から5 cm、側面または上部に1 cmの空きスペース、デバイスの背面から試験箱まで5 cmの距離を置いて配置します。全体的な配置は、家庭用テレビキャビネットをシミュレートするのに似ています。
通常および異常な動作条件 - ノイズフィルタリングと基本波の復元 一部のデジタルアンプ回路のノイズは、オーディオ信号とともにスピーカーに送信され、オシロスコープがスピーカーの出力波形を検出すると、無秩序なノイズが発生します。以下の図に示す単純な信号フィルタリング回路を使用することをお勧めします(使用方法は次のとおりです。ポイントAとCはスピーカー出力端に接続され、ポイントBはオーディオアンプの基準グラウンド/ループグラウンドに接続され、ポイントDとEはオシロスコープ検出端に接続されます)。これにより、ほとんどのノイズをフィルタリングし、1000Hzの正弦波基本波を大幅に復元できます(図の1000Fは誤植であり、1000pFである必要があります)。![]()
一部のオーディオアンプは優れた性能を発揮し、ピーク歪みの問題を解決できるため、最大出力電力状態に調整しても信号が歪んだりクリッピングしたりすることはありません。この場合、クリッピングのない出力電力は最大出力電力と同等です。目に見えるクリッピングを確立できない場合、最大出力電力はクリッピングのない出力電力と見なすことができます。
電気エネルギー源の分類と安全保護
オーディオアンプは高電圧オーディオ信号を増幅して出力できるため、オーディオ信号エネルギー源を分類して保護する必要があります。分類する際は、トーンコントローラーをバランスの取れた位置に設定して、オーディオアンプがスピーカーに対して最大クリッピングのない出力電力で動作できるようにしてください。次に、スピーカーを取り外し、開放電圧をテストします。オーディオ信号エネルギー源の分類と安全保護を以下の表に示します。
|
オーディオ信号電気エネルギー源の分類と安全保護 |
|||
|
エネルギー源レベル |
オーディオ信号RMS電圧(V) |
エネルギー源と一般の人々の間の安全保護の例 |
エネルギー源と指示された人員の間の安全保護の例 |
|
ES1 |
≤71 |
安全保護は不要 |
安全保護は不要 |
|
ES2 |
>71および≤120 |
端子絶縁(アクセス可能な部品は非導電性): ISO 7000 0434aコード記号を示します |
安全保護は不要 |
|
端子が絶縁されていない(端子が導電性またはワイヤが露出している): 「絶縁されていない端子またはワイヤに触れると不快感を引き起こす可能性があります」などの指示的な安全上の注意でマークします |
|||
|
ES3 |
>120 |
IEC 61984に準拠し、IEC 60417の6042コード記号でマークされたコネクタを使用 |
|
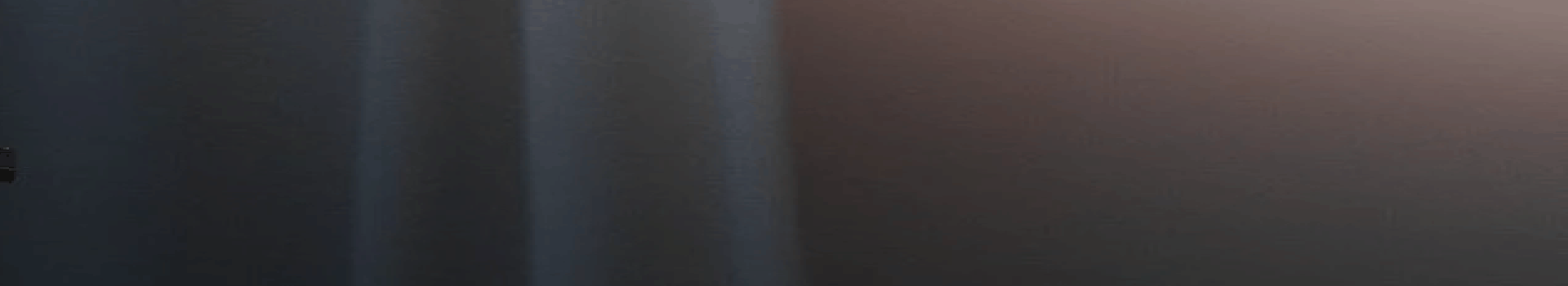
IEC 62368-1 オーディオアンプを搭載した機器の試験要件
ITU-R 468-4(サウンド放送におけるオーディオノイズレベルの測定)の仕様によると、1000Hzの周波数応答は0dB(以下の図を参照)であり、基準レベル信号として適しており、周波数の評価に便利です。![]()
オーディオアンプの応答性能。ピーク応答周波数信号。 メーカーがオーディオアンプが1000Hz条件下で動作しないことを宣言する場合、オーディオ信号源周波数はピーク応答周波数に置き換える必要があります。ピーク応答周波数は、オーディオアンプの意図された動作範囲内で、定格負荷インピーダンス(以下、スピーカーと呼ぶ)で最大出力電力を測定したときの信号源周波数です。実際の操作では、検査官は信号源振幅を固定し、周波数をスイープして、スピーカーに現れる最大実効値電圧に対応する信号源周波数がピーク応答周波数であることを確認できます。
最大出力電力は、スピーカーが取得できる最大電力であり、対応する電圧は最大実効値電圧です。一般的なオーディオアンプは、クラスABアンプの動作原理に基づいてOTLまたはOCL回路をよく使用します。1000Hzの正弦波オーディオ信号がオーディオアンプに入力され、増幅領域から飽和領域に入ると、信号振幅は増加を続けることができず、ピーク電圧点が制限され、フラットトップ歪みがピークに現れます。
オシロスコープを使用してスピーカーの出力波形をテストすると、信号が実効値まで増幅され、それ以上増加できなくなると、ピーク歪みが発生することがわかります(図2を参照)。このとき、最大出力電力状態に達したと見なされます。ピーク歪みが発生すると、出力波形のクレストファクターは、1.414の正弦波クレストファクターよりも低くなります(図2に示すように、クレストファクター=ピーク電圧/実効値電圧= 8.00 / 5.82≈1.375<1.414)![]()
図2:1000Hz正弦波信号入力条件、最大出力電力時のスピーカー出力波形
出力電力タイプと調整 - クリッピングのない出力電力クリッピングのない出力電力とは、スピーカーが最大出力電力で動作し、ピーク歪みがない場合の、飽和ゾーンと増幅ゾーンの接点での出力電力を指します(動作点は増幅ゾーンに偏っています)。オーディオ出力波形は、ピーク歪みやクリッピングのない完全な1000Hz正弦波を示し、そのRMS電圧も最大出力電力でのRMS電圧よりも低くなります(図3を参照)。
![]()
図3は、増幅率を下げた後の、クリッピングのない出力電力状態に入るスピーカーの出力波形を示しています(図2と3は同じオーディオアンプネットワークを示しています)
オーディオアンプは増幅領域と飽和領域のインターフェースで動作し、不安定であるため、信号振幅のジッター(上部と下部のピークが等しくない可能性がある)が発生する可能性があります。クレストファクターは、50%ピークツーピーク電圧をピーク電圧として使用して計算できます。図3では、ピーク電圧は0.5 × 13.10V = 6.550V、RMS電圧は4.632Vです。クレストファクター= ピーク電圧/ RMS電圧= 6.550 / 4.632≈ 1.414.出力電力タイプと調整 - 電力調整方法。オーディオアンプは、小さな信号入力を受け取り、それを増幅してスピーカーに出力します。ゲイン比は通常、詳細な音量スケールを使用して調整されます(たとえば、テレビの音量調整は30から100ステップの範囲です)。ただし、信号源振幅を調整してゲイン比を調整することは、はるかに効果がありません。信号源振幅を下げると、アンプのゲインが高くても、スピーカーの出力電力は大幅に低下します(図4を参照)。![]()
図4:信号源振幅を下げた後、スピーカーがクリッピングのない出力電力状態に入るときの出力波形。
(図2と4は同じオーディオアンプネットワークを示しています)
図3では、音量を調整すると、スピーカーは最大出力電力からクリッピングのない状態に戻り、RMS電圧は4.632Vです。図4では、信号源振幅を調整することにより、スピーカーは最大出力電力状態からクリッピングのない出力電力状態に調整され、実効値電圧は4.066Vです。電力計算式によると
出力電力=電圧RMSの2乗/スピーカーインピーダンス
図3のクリッピングのない出力電力は、図4のクリッピングのない出力電力を約30%上回っているため、図4は真のクリッピングのない出力電力状態ではありません。
最大出力電力状態からクリッピングのない出力電力状態に呼び戻す正しい方法は、信号源振幅を固定し、オーディオアンプの増幅率を調整すること、つまり、信号源振幅を変更せずにオーディオアンプの音量を調整することです。
オーディオアンプの通常の動作条件は、現実世界のスピーカーの最適な動作条件をシミュレートするように設計されています。現実世界の音響特性は大きく異なりますが、ほとんどの音のクレストファクターは4以内です(図5を参照)。![]()
図5:クレストファクターが4の現実世界の音波形
図5の音波形を例にとると、クレストファクター=ピーク電圧/ RMS電圧= 3.490 / 0.8718 = 4。歪みのないターゲットサウンドを実現するには、オーディオアンプは最大ピークがクリッピングしないことを確認する必要があります。1000Hzの正弦波信号源を基準として使用する場合、波形が歪みのないままで、3.490Vのピーク電圧が電流制限されないようにするには、RMS信号電圧は3.490V / 1.414 = 2.468Vである必要があります。ただし、ターゲットサウンドのRMS電圧はわずか0.8718Vです。したがって、ターゲットサウンドの1000Hz正弦波信号源のRMS電圧に対する低減率は0.8718 / 2.468 = 0.3532です。電力計算式によると、電圧RMS低減率は0.3532であり、これは出力電力低減率が0.3532の2乗であり、約0.125 = 1/8であることを意味します。
したがって、スピーカーの出力電力を1000Hz正弦波信号源に対応するクリッピングのない出力電力の1/8に調整することにより、歪みのないクレストファクターが4のターゲットサウンドを出力できます。言い換えれば、1000Hz正弦波信号源に対応するクリッピングのない出力電力の1/8は、クレストファクターが4のターゲットサウンドを損失なしに出力するためのオーディオアンプの最適な動作状態です。
オーディオアンプの動作状態は、スピーカーが1/8クリッピングのない出力電力を提供することに基づいています。クリッピングのない出力電力状態では、音量を調整して、実効値電圧が約35.32%、つまり1/8クリッピングのない出力電力に低下するようにします。ピンクノイズは実際の音に近いため、1000Hz正弦波信号を使用してクリッピングのない出力電力を取得した後、ピンクノイズを信号源として使用できます。ピンクノイズを信号源として使用する場合は、以下の図に示すように、ノイズ帯域幅を制限するために帯域通過フィルターを取り付ける必要があります。![]()
通常および異常な動作条件 - 通常の動作条件
さまざまなタイプのオーディオアンプ機器は、通常の動作条件を設定する際に、以下のすべての条件を考慮する必要があります。
- オーディオアンプの出力は、最も不利な定格負荷インピーダンス、または実際のスピーカー(提供されている場合)に接続されています。
——すべてのオーディオアンプチャンネルが同時に動作します。
- トーンジェネレーターユニットを備えたオルガンまたは同様の楽器の場合、1000 Hzの正弦波信号を使用する代わりに、2つのベースペダルキー(ある場合)と10個のマニュアルキーを任意の組み合わせで押します。すべてのストップと出力電力を増加させるボタンを有効にし、楽器を最大出力電力の1/8に調整します。
- オーディオアンプの意図された機能が2つのチャンネル間の位相差によって決定される場合、2つのチャンネルに適用される信号間の位相差は90°です。
マルチチャンネルオーディオアンプの場合、一部のチャンネルが独立して動作できない場合は、定格負荷インピーダンスを接続し、出力電力をアンプの設計されたクリッピングのない出力電力の1/8に調整します。
連続動作が不可能な場合、オーディオアンプは連続動作を可能にする最大出力電力レベルで動作します。
通常および異常な動作条件 - 異常な動作条件
オーディオアンプの異常な動作条件は、通常の動作条件に基づいて発生する可能性のある最も不利な状況をシミュレートすることです。スピーカーは、音量を調整したり、スピーカーを短絡させたりするなどして、ゼロと最大出力電力の間の最も不利な点で動作させることができます。
通常および異常な動作条件 - 温度上昇試験配置
オーディオアンプの温度上昇試験を実施する場合は、メーカーが指定した位置に配置してください。特別な記載がない場合は、前面が開いた木製の試験箱に、箱の前面から5 cm、側面または上部に1 cmの空きスペース、デバイスの背面から試験箱まで5 cmの距離を置いて配置します。全体的な配置は、家庭用テレビキャビネットをシミュレートするのに似ています。
通常および異常な動作条件 - ノイズフィルタリングと基本波の復元 一部のデジタルアンプ回路のノイズは、オーディオ信号とともにスピーカーに送信され、オシロスコープがスピーカーの出力波形を検出すると、無秩序なノイズが発生します。以下の図に示す単純な信号フィルタリング回路を使用することをお勧めします(使用方法は次のとおりです。ポイントAとCはスピーカー出力端に接続され、ポイントBはオーディオアンプの基準グラウンド/ループグラウンドに接続され、ポイントDとEはオシロスコープ検出端に接続されます)。これにより、ほとんどのノイズをフィルタリングし、1000Hzの正弦波基本波を大幅に復元できます(図の1000Fは誤植であり、1000pFである必要があります)。![]()
一部のオーディオアンプは優れた性能を発揮し、ピーク歪みの問題を解決できるため、最大出力電力状態に調整しても信号が歪んだりクリッピングしたりすることはありません。この場合、クリッピングのない出力電力は最大出力電力と同等です。目に見えるクリッピングを確立できない場合、最大出力電力はクリッピングのない出力電力と見なすことができます。
電気エネルギー源の分類と安全保護
オーディオアンプは高電圧オーディオ信号を増幅して出力できるため、オーディオ信号エネルギー源を分類して保護する必要があります。分類する際は、トーンコントローラーをバランスの取れた位置に設定して、オーディオアンプがスピーカーに対して最大クリッピングのない出力電力で動作できるようにしてください。次に、スピーカーを取り外し、開放電圧をテストします。オーディオ信号エネルギー源の分類と安全保護を以下の表に示します。
|
オーディオ信号電気エネルギー源の分類と安全保護 |
|||
|
エネルギー源レベル |
オーディオ信号RMS電圧(V) |
エネルギー源と一般の人々の間の安全保護の例 |
エネルギー源と指示された人員の間の安全保護の例 |
|
ES1 |
≤71 |
安全保護は不要 |
安全保護は不要 |
|
ES2 |
>71および≤120 |
端子絶縁(アクセス可能な部品は非導電性): ISO 7000 0434aコード記号を示します |
安全保護は不要 |
|
端子が絶縁されていない(端子が導電性またはワイヤが露出している): 「絶縁されていない端子またはワイヤに触れると不快感を引き起こす可能性があります」などの指示的な安全上の注意でマークします |
|||
|
ES3 |
>120 |
IEC 61984に準拠し、IEC 60417の6042コード記号でマークされたコネクタを使用 |
|